
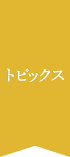
トピックス
シェアリングエコノミーとは?
〜押さえておきたい4つのポイントと新型コロナウイルス感染拡大の影響〜
2018.03.20公開
2021.07.30更新
【その1】シェアリングエコノミーとは?
シェアリングエコノミーとは、所有しているモノや場所・スキルなどをインターネット上のプラットフォームを介して、個人間でシェア(貸借・売買・提供)していく新しい経済の動きです。
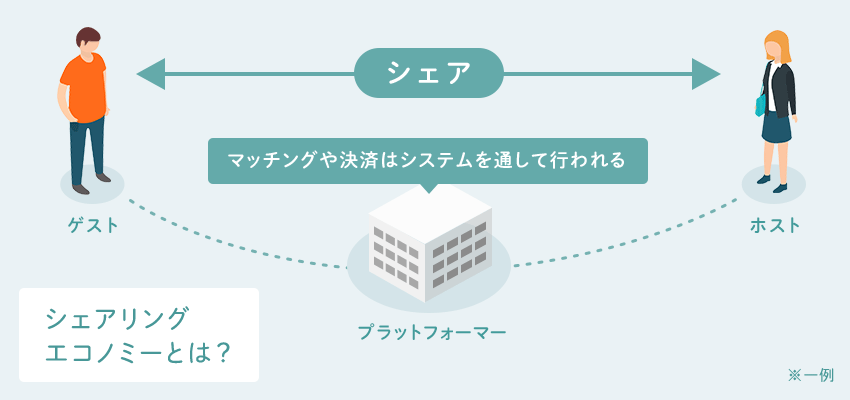
シェアリングエコノミーが生まれた背景には、インターネットやスマートフォンといった技術の進歩と普及があります。つまり、テクノロジーの進化によって多くの人が位置情報や決済システムといったサービスを利用しやすくなり、個人間でのシェアが手軽にできるようになったのです。
海外では2008年頃から米国シリコンバレー発の「民泊仲介サービス」や「配車サービス」などを筆頭に普及が始まりました。その後、日本でも海外旅行先でシェアサービスを利用したユーザーの口コミが、SNSで広まるなどしてメディアでも話題を呼びました。
こうした流れの中で、若い世代を中心に「必要なときに必要なぶんをシェアしあう」ライフスタイルが支持を集めるようになったのです。
日本政府も地方創生や超少子高齢化社会における諸課題の解決に、シェアリングエコノミーが寄与すると期待を寄せ、シェアリングエコノミー推進を成長戦略の重点施策の一つに位置づけています。2016年11月にはシェアリングエコノミー検討会議でシェアリングエコノミー推進プログラムを策定。2017年1月には内閣官房IT総合戦略室内に「シェアリングエコノミー促進室」が設置されました。

サステナブルな人
また2017年6月には、シェアリングエコノミー検討会議で示されたシェアリングエコノミー・モデルガイドラインに基づき、一般社団法人シェアリングエコノミー協会が自主ルールを策定し、その適合を認証審査する「シェアリングエコノミー認証制度」が開始されました。
【その2】シェアリングエコノミーの市場規模は?
総務省の「平成28年版情報通信白書」によれば、全世界のシェアリングエコノミーの市場規模は、2013年には約150億ドル(約1兆7000億円)だったものが、2025年には約3350億ドル(約37兆円)にまで拡大すると予測されています(出典はPwC「The sharing economy - sizing the revenue opportunity」)。

日本国内の市場規模は、2019年度には約1,132億円。約503億円だった2016年度時点では、2021年度に約1071億円に達すると予測されていましたが、予測を上回るペースで拡大しています。(出典は矢野経済研究所「シェアリングエコノミー(共有経済)国内市場規模推移と予測」2020年)。
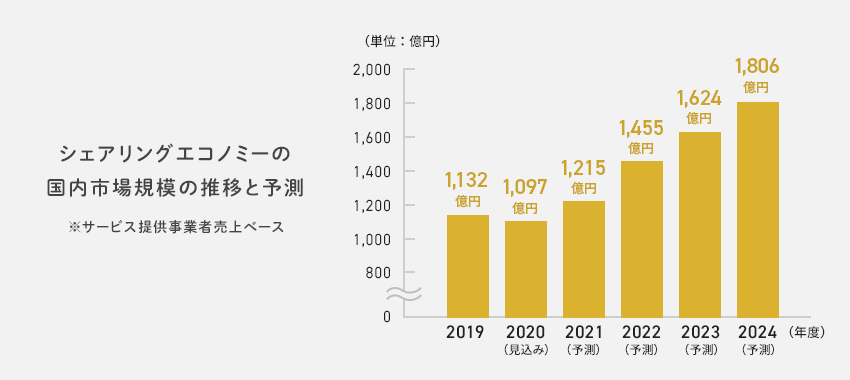
【その3】シェアリングエコノミーには、どんなサービスがある?
シェアリングエコノミーのシェアサービスは、主に「空間」「モノ」「移動」「仕事」「お金」の5つのカテゴリーに分類されます(下の表参照)。サービスの形態はさまざまですが、ネット上でやりとりが完結するオンライン型、直接対面するオフライン型に分けられます。
また、個人間でサービスを享受しあうCtoC(Consumer to Consumer)のモデル以外にも、企業が複数の個人にモノやサービスを提供するBtoC(Business to Consumer)のモデルもシェアリングエコノミーに該当します。
シェアリングエコノミーの領域

【その4】最近、耳にする「シェアリングシティ」とシェアリングエコノミーの関係は?
シェアリングシティとは、シェアリングエコノミーのサービスを活用して、地域課題の解決に取り組む都市を指します。シェアリングエコノミー協会では2017年11月から、シェアリングシティ宣言を行った自治体で、一定条件を満たす自治体に対して「シェアリングシティ認定マーク」を無償で授与しています。2020年3月現在で19の自治体が認定都市となりました。

シェアリングシティ認定マーク
鹿児島県奄美市/滋賀県大津市/石川県加賀市/岩手県釜石市/長野県川上村/福井県鯖江市/
長崎県島原市/佐賀県多久市/千葉県千葉市/北海道天塩町/富山県南砺市/宮崎県日南市/
静岡県浜松市/秋田県湯沢市/埼玉県横瀬町/山梨県小菅村/北海道中頓別町/岐阜県関市/群馬県桐生市

サステナブルな人
2020年7月には、認定プロジェクトを引き継ぐ「シェアリングシティ推進協議会」が設立され、2021年6月現在 60自治体が会員となっています。また、2021年3月に内閣官房シェアリングエコノミー促進室が全国115のシェアリングエコノミー活用事例を公表しました。就業機会の創出や観光振興、需給ひっ迫の解消、地域の足の確保、子育て支援や防災といった地域課題に対応するプロジェクトが全国で生まれています。
雇用不足による人口流出の課題を抱える佐賀県多久市では、2016年11月にシェアサービスを通じた就業機会の創出を目的として「多久市ローカルシェアリングセンター」を開設し、サポートを行っています。
同センターでは、自宅でインターネットを通して個人が企業などから仕事を請け負うクラウドワーカーを育成するためのプログラムが実施され、子育て中の主婦や70代のシニア層などが研修生として参加しています。修了生はクラウドソーシングサービスを通じて、自分の得意分野でスキルを発揮して働くことを目指しています。
また、過疎化が進む北海道天塩町では、相乗りシェアサービスと連携して地域に暮らす人がドライバーとなり、地域間の移動を支え合う取り組みが2017年から始まっています。そのほかのシェアリングシティでも、公助から共助の地方創生を目指し、サステナブルな街づくりが進められています。
【その5】コロナ禍・ポストコロナ時代のシェアリングエコノミー
人と人の物理的な接触を避けざるをえないコロナ禍において、シェアリングエコノミーが持つ意味も変わりつつあります。石山アンジュさんにお聞きしました。

サステナブルな人
緊急事態宣言下、ドクターシェアリングサービスが期間限定で医師への相談を無償化し、空間シェアリングサービスが医療従事者に向けて無料で宿泊場所を提供するなど、新たな共助のモデルが生まれました。
地方などに分散的に拠点を持ちやすくする空間シェアリングサービスでは、2019年は利用者の大半がフリーランスや個人事業主でしたが、現在は会社員の利用者数が上回っています。
スキルシェアサービスにおいては、海外出張に行けなくなった企業がオンラインでの海外調査案件を依頼するケースが増えたり、オンライン料理講座に多くの方が集まるなど、利用者が増加しました。
このほか、隙間時間を使って仕事がしたい個人と、単発・短時間で臨機応変に人手不足を解消したい事業者をマッチングする”時間のシェア”とも呼べるサービスも、多く利用されました。時間のシェアサービスは、スキルシェアサービスと同様に契約がないだけでなく、隙間時間に対して報酬が支払われるため成果物を収める義務もなく簡便に利用できます。このため、コロナ禍で需要が激減した飲食店から需要が激増した物流へ、人材の流動をスムーズにしました。
リアルでの接触が厳しく制限される中、シェアリングエコノミーは、人々が社会との接点を新たに見いだし、仕事や生活を維持したり、より豊かにしたりする活路として重宝されるようになりました。こうした変化を経たポストコロナ時代においては、新しいライフスタイルの受け皿としてますます注目を集めるはずです。

















